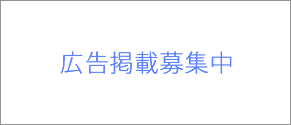時間と労力は最小で、最大の成果を得る! 初心者でもAIの一歩踏み込んだ使い方が分かる解説書 -AI独学超大全
Post on:2025年11月20日
sponsorsr
※本ページは、アフィリエイト広告を利用しています。
ChatGPTやGeminiなどAIを使ってみたけど、なんかいまいち、自分で調べてやった方が楽、そんな人にお勧めのAIを仕事や生活にどのように取り組むと効果があがるかを解説した良書を紹介します。
特になんとなく生成させてるだけという人に、AIの一歩踏み込んだ使い方が分かる解説書です。私も本書を読んで、AIをもっと楽しく活用するぞと思いました。

本書は先月発売され、Amazonでしばらくベストセラーが続いていた書籍で、私も発売早々に入手したのですが、ここで紹介するのがすこし遅れてしまいました。
著者は佐藤 勝彦氏、1000時間AIと対話して編み出した「AIをどう使いこなし、何を創造するか」をさまざまな事例で実践的な使い方を惜しみなく解説したのが本書です。AIの使い方の解説書として、また啓発本として、さらには読み物としても楽しめる一冊です。
Kindle版も同時発売されます!
巻末の付録も非常に豪華で、本書の内容をすべて学習済みのAIが読書体験を強力にサポートしてくれます。理解できない箇所を解説してくれたり、本書のノウハウをあなた用に最適化して具体的なアクションプランを提示してくれたり、新しい読書体験が楽しめます。
版元様より許可をいただいたので、紙面のキャプチャを少しだけご紹介。

本書はChatGPT-4が登場してから一日10時間、100日間で1000時間、著者自身がAIと対話して編み出した「AIをどう使いこなし、何を創造したいか」その方法論を解説したものです。
かなり深いところまで詳しく解説されており、この記事だけでは紹介しきれないので、多くの人が入り口となるページをピックアップして紹介しています。

本書は大別して、具体化、抽象化、構造化の3部構成。第1部の具体化は4章構成で、AIをどのようにするのか50個の具体的な事例が解説されています。
具体化では、左ページにテーマ解説、右ページが具体的なやり方が分かります。

第1章は初級編として、日常生活の中でAIを活用するテクニックです。TODOリストや心配事でごちゃごちゃになった頭の中をAIと対話することでスッキリ整理したり、移動中や就寝前に浮かんだアイデアをAIを通じて構造化メモを作成したり、毎朝のニュースチェックをAIに任せたり、GmailやGoogleドライブから欲しい情報をAIで瞬時に取り出す方法など、日常的なことの効率がかなりアップします。

具体化の第2章は、独学に役立つAIの活用方法。たとえば、1ヵ月くらい一日のコンディション・やる気度をAIに報告しておくと、日時や活動が自分の生産性とどのような相関関係があるのかが分かります。運動の後に集中力があがったり、長い会議の翌日は生産性が低下するなど、意識することで戦略的な時間管理がおこなえます。

具体化の第3章は学び。英語のWebページを翻訳させたり、すでにAIを活用している人もいると思いますが、ここではさらに一歩進めて、AIを相手に英会話の勉強をすることもできます。AIなら、時間に縛られることもなく、自分の好きな時間に好きなだけ英会話の勉強ができます。もちろん、AIに間違いを修正してもらったり、AIに良い点を褒めてもらったり、実践的な練習ができます。

AIに質問しても、当たり障りのない答えしか返ってこない。アイデア出しをお願いしても、いまいち。そんなときはAIに考えるプロセスを指示することで、質の高い回答を得ることができます。AIにいきなり回答を求めるのではなく、その回答に至るまでの論理的なステップを1つずつ説明させることで、AIはより深く慎重に思考するようになり、回答の品質が向上します。

具体化の最後第4章は、これまでのAI活用方法を統合し、より高度な創造的な使い方です。AIを単なる便利ツールとしてだけでなく、自分専用のパートナーとして昇華させます。仕事の面でも、生活の面でも、AIはパートナーとして活躍します。
たとえば、生活面だと過去に読んだ本のリストを作成し、その中で特に良かった本や感銘を受けた本などのメモを加えて精度を高めてAIに伝えると、AIはそれを分析し、隠れた興味のパターン、嗜好の方向性、必要な栄養となる本などを分析・推奨させることができます。

第2部となる「超抽象化」では、第1部とはまったく異なり、ストーリー形式でAIをどのように実践的に活用するかです。登場人物はAIをスキルを持つ京子、昭和の営業スタイルを体現する達也の二人がメイン、第1部でも取りあげられたAI活用方法を実践的に使用し、思考OSがアップデートされる瞬間を楽しめます。

AIにコードを書かせるバイブコーディングに興味がある人も多いと思います。バイブ(Vibe)とは「雰囲気」の意で、プログラマーは技術的なことにこだわるのではなく、機能や目的の全体的な雰囲気をAIに伝えて細かいことは任せるコーディング手法です。現在では非エンジニアリングでもアプリやシステムを構築した、といった事例が豊富にあります。

最後となる第3部は「超構造化」AIの活用レベルが構造的にまとめられており、初級編では1日1時間の7日間プログラムとしてAIをどのように活用していくかが詳しく解説されています。

1日目はAIとの対話。初級レベルでは簡単な挨拶と質問をするくらいです。中級レベルは構造化した相談をし、上級レベルになるとAIに役割を与えて専門的な対話をおこなえるようになります。こんな感じで1日1時間の7日間プログラムが紹介されています。

中級編では、AIを活用したチームマネジメント。AIは個人だけでなく、チームという組織でも活躍します。この中級編では14日間のプログラムが用意されています。

最後の上級編は、AIで創るクリエイティブ。前述のバイブコーディングもその一つですが、ここではさまざまなジャンルにおいてアイデアを実装するを実現します。たとえば、英語だと英語の記事を翻訳、記事の要点を要約、AIを家庭教師に見立てて専門用語の解説、AIとの対話による洞察の抽出、記事に対する個人的な見解を開発、という段階があります。
AI独学超大全の目次

AI独学超大全の目次

AI独学超大全の目次

AI独学超大全の目次

AI独学超大全の目次
さすがに一日10時間とはいきませんが、私も本書を読んで、AIと向き合う時間が増えました。これまでは何となく問いかけていたり、無駄に生成させたりしていたことが多かったですが、AIとの対話のこつが分かると使い方も大きく変わることを実感しました。
献本の御礼
最後に、献本いただいたSBクリエイティブの担当者さまに御礼申し上げます。
当サイトでは随時、献本を受け付けています。
お問い合わせは下記よりお願いいたします。
sponsors