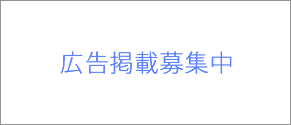それがまさに知りたかった! イラストはちょっとしたコツが分かると楽しくなる、イラスト解説書の決定版 -キャラクターイラスト基本の「き」
Post on:2025年8月29日
sponsorsr
※本ページは、アフィリエイト広告を利用しています。
どのジャンルでもそうですが、ちょっとしたコツが分かるとメキメキ腕があがることがあると思います。
キャラクターのイラストを描いてみたい、いろいろな表情、肌や目や髪の塗り、さまざまなポーズ・アクション、服装や装備、小物まで、イラストを描くノウハウがぎっしり詰まった解説書を紹介します。

著書は、鳥好きのサッサ氏(@sassa_tori)、専門学校でイラストやデッサンの指導に従事し、ゲームイラストやグッズイラスト(幻想水滸伝など)の制作も手がけているイラストレーターさんです。購入した際には、裏表紙の自画像?にも注目です。
本書はそんな氏による初の単独書籍で、イラストの指導に従事してきたプロが考え抜いたかなり充実したイラストの解説書となっています。解説に使われているイラストは3,000点以上! すべてのイラストがこの解説書のためだけの描き下ろしで、208ページすべてにイラストを描くノウハウがぎっしり詰まっています。
本書は今週発売されたばかりで、Kindle版も同時発売!
けっこう細かく書いてあるページも多いので、お勧めは書籍版です。
版元様より許可をいただいたので、紙面のキャプチャを少しだけご紹介。

著者のサッサ氏からのメッセージです。
『「絵の練習をし始めた頃の自分に届けたい」と思うような内容を形にしました。眺めるだけでも楽しめる一冊になるように全力を尽くしましたので、手にとっていただけたら嬉しいです!』(@sassa_toriより)
まさに、「全力」の気合いが感じられる一冊でした! イラストの描き方の解説も非常に詳しく、理解しやすい考え方、身につきやすい練習法などがよく分かります。

本書は8章構成で、88のキーポイントが収録されています。第1章は「身体」アタリ・ラフの描き方から始まります。イラストの解説書で最初にツールの説明が2章くらい続く書籍だとがっかりしますよね。本書はそんなことはありません!
イラストを描くツールは、何か特別なものが必要ということではなく、クリスタでもPhotoshopでもProcreateでも何でも大丈夫です。

88のキーポイントは、見開きページで完結します。左上にはキーポイントごとに「目標」が書いてあり、「正面顔の基本」では「顔の中の比率を意識できるようになろう」です。目の位置、左右の目の間隔、パーツの大きさと意味の比率に注目して描くようにします。また、右下の黄色は「練習」で、実際に手を動かして練習する課題です。

第1章「身体」のキーポイントは細かく分かれており、「アタリとは?」「正面顔の基本」からはじまり、横顔、髪、身体のバランス、身体の起伏、骨・筋肉の構造、首・肩・胴の構造、腰の構造、腕・手の構造、脚・足の構造の全11キーポイントです。
この章だけで、すでに普通のイラスト書の半分くらいの充実度です。

第2章は「視点」視点とは対象物を真横から見るか、下から見上げるのか(アオリ)、上から見下ろすのか(俯瞰)です。特に、アオリと俯瞰で見た時に対象物の面の角度がどのように変化するのか知ることが、イラストを描くときのポイントです。

第3章は「アクション」前章でイラストを立体的な視点でみることができるようになったので、さまざまなアクションを描くことに役立ちます。身体の部位ごとに可能な動きがあり、見えない部分のアタリを想像して描くようにします。
文章だけ見ると、そんな簡単にはできないよと思うかもしれませんが、11のキーポイントを順番に読み進めるとなんだかできるようになる気がします。

第4章は本書のタイトルにもある「キャラクターデザイン」キャラクターの特徴と差別化になる各要素を描きます。目の描き方一つをとってみても、大きさ・角度・縦横の比率・開き具合・白目黒目の比率など、ちょっとした違いが大きな特徴となり、差別化にもなります。そして眉と組み合わせることで、また違った印象を与えます。

髪を描くときにも注目しておくポイントがいくつかあります。髪のバリエーションを増やしたいときは、ヘアカタログとかを見ると髪型の分析ができます。

第5章はこれまたキャラクターの重要な要素「衣服・装備」服を描くのって難しいですよね。ポイントは平面ではなく、立体として描くことです。たとえば、スカートは台形ではなく、プリン形に描くとうまくいきます。

服には素材の違いがあったり、服のシワがあったり、さらにはパーツや小物がいっぱいある複雑な服があったりと本書ではそれぞれの描き方にについて学べます。

また「衣服・装備」装備では、靴、帽子やメガネなどの身につける小物、さらには鎧や武器といったものもキャラクターイラストならではの要素です。

第6章は「背景・構図」イラストを描くときによく使われるのは、3種類の透視図法です。一点透視・二点透視・三点透視で大事なのはパースの方向に沿って描くことです。さらに、奥行き感の出し方、イラストにおける視線誘導など、さまざまなテクニックを学べます。

第7章は「陰影・線・色」キャラクターや物などは、陰(光源の反対側にできる物体につく暗い部分)と影(光源の反対側にできる地面や壁に落ちる暗い部分)の関係で立体感が生まれます。質感の違いは光の反射や屈折や陰影で生まれ、イラストを描くときはこの陰影を色や線で表現します。

肌や目を塗るときも陰影と質感を意識すると、イラストの表現の幅が広がります。

最後の第7章は「いろいろなモチーフ」犬やネコや馬などの哺乳類をはじめ、鳥類、は虫類、両生類、魚類、昆虫などの描き方のポイントが解説されています。さらに、モンスターやドラゴン、獣人、ロボットなどもあります。

また、キャラクターのイラストにはいろいろなエフェクトや質感表現が必要になるでしょう。炎、水、氷、風、雷、空、などそれぞれの質感の描き方が分かります。
キャラクターイラスト基本の「き」の目次

キャラクターイラスト基本の「き」の目次

キャラクターイラスト基本の「き」の目次
全208ページに渡り、イラストを描くためのノウハウがぎっしり詰まった一冊でした。1ページあたり10点以上の描き下ろしイラストが使用されており、しかも全ページフルカラー、こんなにお安いお値段でいいんですか? と思ってしまいました。
イラストをこれから学びたい人だけでなく、長年イラストを描いてきた人の復習としてもかなりお勧めです!
献本の御礼
最後に、献本いただいたビー・エヌ・エヌの担当者さまに御礼申し上げます。
当サイトでは随時、献本を受け付けています。
お問い合わせは下記よりお願いいたします。
sponsors