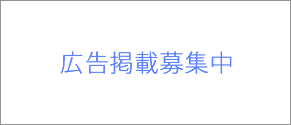プロはこうやって伝えていたのか! 口頭やメール、デザインにも通じる伝え方において表現のスキルを磨ける一冊 -伝え方
Post on:2023年10月20日
sponsorsr
※本ページは、アフィリエイト広告を利用しています。
伝えたいことがうまく伝わらない、口頭や文章のコミュニケーションだけでなく、デザインにおいて伝えたいことがうまく伝えられないこともあります。
料理のおいしさが伝わらない
商品の良さが伝わらない
想いをうまく伝えられない
ブログの記事を読んでもらえない
デザインがクライアントの期待に応えられない
伝え方に正解はありません、しかしその原則は文章もデザインも同じ。
編集家の第一人者による「伝え方」の解説書を紹介します。

著者は「編集家」の松永 光弘氏、編集やコミュニケーションの講演や執筆をはじめ、クリエイティブ系の書籍も多数企画・編集されているので、お名前にピンときた人も多いと思います。当ブログで紹介した書籍だと『「アタマのやわらかさ」の原理。』(紹介記事)があります。
そんな著者による、伝え方の解説書。文章での伝え方はもちろん、プレゼン、メール、そしてデザインで「伝えるために、何が足りなかったのか」が分かります。
Kindle版も同時発売されています!
著者様より許可をいただいたので、紙面のキャプチャを少しだけご紹介。

本書は4章構成で、編集家として文章に限らずさまざまな「伝える」に携わってきた著者による、プロがたどり着いたシンプルな「伝え方」の原則がよく分かる解説書です。なんとなくしか考えていなかったことが言語化されており、気づきも多くあると思います。
『はっきりわかっているから、はっきり伝えることができる』これは正にそうですね。使用しているからこそ、理解しているからこそ、「分かる」ことがあります。

第1章は、伝えるコミュニケーションとはどういうものなのか。「伝える」というのは話しで伝えるをはじめ、文章で伝える、デザインで伝えるなど、形態や用い方はさまざまですが、何かしらの表現物です。

デザインで考えると分かりやすいかもしれません。たとえば、講義の紹介記事に使用する写真画像を選ぶときに、講義だから受講風景の写真にしよう、いい表情だから笑顔の受講者の写真にしよう、と思ったとします。しかし、そこにメッセージや一貫性がなければ記事を読んだ人はその写真に違和感を感じるでしょう。
「特別な緊張感のおかげでふだん以上に集中でき、多くの学びを得られる」を「伝えるべきこと」だとしたら、緊迫感のある受講風景であったり、真剣に学んでいる受講者の写真が適している、と判断できます。

第2章は、魅力の伝え方。私は情報や商品の良さを伝えるときには「ベネフィット」を意識していますが、「よさ」と「わけ」はそれに通じるものがありますね。

単なる文章では伝わらないことでも、「よさ」や「わけ」を明確に提示することで「気づき」を与えることができ、より効果的にメッセージを伝えることができます。

『既知にも、未知にも、人は惹かれない』
SNSでの投稿、動画やブログのタイトルなどを考えるときに、この言葉を念頭に置いておくとよいかもしれません。「既知」はすでに知っているので興味が引かれません、「未知」は知らないので興味をもちづらいでしょう。
人が惹かれるのは「既知と未知の間」にあります。知っているけどそこまで知っていない、その意味や価値に気がついていない、そういったものに人は惹かれます。

最後の第4章は、では「伝える」にはどうすればよいか。
文章モデルの一つとして「起承転結」がありますが、「伝える」には通用しづらいというのが現状です。「起承転結」は最初から最後まで読んでもらえることが前提になっていますが、どんな意味があるのか分からないまま起から読むのは苦痛になります。さらに承転も同様で、結を読むまでに離脱してしまう可能性があります。

「伝える」ために効果があるのが、著者が提案する「同分解展」モデルです。これは「起承転結」で構成するのではなく、「同意、分析、解決、展望」で構成します。これには前述の「よさ」と「わけ」も組み込まれており、たとえば、「こんな悩みはありませんか?」(同意)「それにはこういう原因があります」(分析・わけが実現されていないことを指摘)「解決にはこれが必要です」(解決・わけの指摘と伝えたいことの提示)「解決したらこうなります」(展望・よさの指摘」となります。このように構成されていると、確かに伝わりやすいですよね。

付録として『「もっと伝える」ための2つのヒント』もあります。「向こう側」と「高さ」という2つの目線は伝えるコミュニケーションにおいて重要な役割を担っています。これらを意識して表現の仕方に工夫をすると、かなり分かりやすく伝えることができます。
伝え方の目次

伝え方の目次

伝え方の目次
今年になって、AIによる文章生成や画像生成が加速化しました。すでに体験した人も多いと思いますが、AIと今後うまく付き合っていくには編集という作業が重要になるかもしれません。思い通りにならない、期待したものと違う、これらはAIにどのように伝えるかが大きな影響を与えます。そして生成されたものをどのように手直しするかも重要です。
本書は伝え方において、さまざまな気づきを与えてくれる一冊でした。
献本の御礼
最後に、献本いただいた著者さまに御礼申し上げます。
当サイトでは随時、献本を受け付けています。
お問い合わせは下記よりお願いいたします。
sponsors