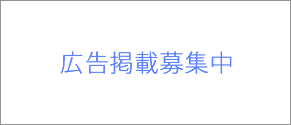異世界や空想世界の創作に役立つ数学、物理、地学、生物学などの知識や技術に溢れた解説書 -空想世界をつくる理科の教科書
Post on:2025年10月10日
sponsorsr
※本ページは、アフィリエイト広告を利用しています。
異世界(特に古代・中世・近世をベースにした空想の世界)を舞台にした小説、マンガ、同人誌を創作するときに、役立つ理科の教科書を紹介します。
作品の内容すべてが空想すぎると読者には伝わりにくいものです。現代の読者が理解できる知識や常識を踏まえた上で、世界観、土地、物理現象、魔法、生物、鉱物、天文、医学、錬金術などをどのように解釈するかを解説したものです。

著者の榎本 海月氏と榎本 秋氏はともに榎本事務所に属している作家さんで、これまでに数多くの小説執筆の指南書を発売されています。本書は『空想世界をつくる理科の教科書』で、物理や地学や生物学など9つの視点から空想世界をつくる技術や知識やツールの成り立ちと歴史を解説したものです。
本書は、先月末に発売されたばかり!
本書は電子書籍化の予定はありません(版元の担当者様に確認済み)。
版元様より許可をいただいたので、紙面のキャプチャを少しだけご紹介。

本書は0+9章構成で、9つの章では物理学、数学、地学、植物学、生物学、鉱物学、天文学、医学・錬金術、魔法学の観点から空想世界を創作するための技術や知識が解説されています。空想世界(古代や中世や近世をモデルにしたファンタジー異世界)では理科的な知識をどのように解釈すればよいのか、読み物としても楽しめます。

本書のコンセプトは、物語創作のための設定です。空想世界・異世界といっても登場人物はそこで生活し、文化や文明があり、技術、場合によっては魔法などもあるかもしれません。そういった設定に矛盾がでないよう、過剰だったり、偏りすぎないようにすることで、読者はその世界観に没頭できます。

では、章の中を見てましょう。
第1章は「物理学」この世界はどんな理屈で動いているのか、世界の根源には何があるのか、といったいわゆる「ものの理」をはじめ、物理学は人々の生活にも密接に繋がっています。

また、いろいろな物理現象もストーリーに必要になることがあります。たとえば、光は現代の科学では「さまざまな電磁波のうち、目に見えるものが光」であり、「光がものに跳ね返って、目に入るから、ものが見える」と理解されています。これが古代・中世では「光はまっすぐ進むもの」「熱を伴うもの」といった光の基本的な性質はすでに理解されていました。

さらに火も重要なアイテムです。人類は火をどのようにして獲得したのか、人類学的アプローチでは山火事や落雷による発火で火と出会ったと考えられています。神話的アプローチでは神が恩恵として火をもたらした、あるいは神の内側から火が生まれた(火の神:カグツチ)とされています。

最初に挙げた「ものの理」、万物の根源も物理学が重要なポイントになります。古代ギリシャの一元論、エンペドクレスの四元論、アリストテレスの五元論では、それぞれ世界は一つの何かから成り立っている、4つの元素が関係しあっている、5つめの特別な元素が存在する、のように古代的な価値観においての元素を深く掘り下げるて解説されています。
こんな感じに各章で20ページ前後、多い章は30ページ以上に渡って、設定に役立つ学問が解説されています。

第3章は科学や技術の基礎となる「数学」、第3章はその世界の土地のあり方や気象などに影響を与える「地学」、第4章は自然に生えている植物をはじめ、衣料や材料にも関係する「植物学」、第5章は人間や動物、そして異種族の「生物学」

第6章は石や金属、宝石など日常にも戦闘にも使われる「鉱物学」、第7章は古代より重要視されていた「天文学」、第8章は病気や怪我、さらには魔術的な要素もある「医学と錬金術、そして化学」、最後の第9章は現代の理科(科学)では解明できない「魔法学」

個人的に興味が惹かれたとこをすこしだけ。
「鉱物学」ではさまざまな金属の解説も充実しています。たとえば、刀剣でよく登場するダマスカス鉱、これは実在する鉱物で、中世中期の十字軍の騎士たちはダマスカス刀を使用していました。また、神話レベルの金属も登場します。オリハルコンは特別な力を秘めた金属としてさまざまなストーリーに登場しますね。ほかにも、ミスリル、アダマンタイト、ヒヒイロカネといったレアな金属の解説も充実しています。

「魔法学」では、実際に使われた魔法が使える道具が解説されています。魔術書をはじめ、鍋、仮面と化粧、楽器、護符、杖、ワンドなどを使用して魔術を使います。また、実際に存在した魔法として、呪術師、仙術、ルーン魔法、陰陽道、ヨーガ、密教、カバラなども詳しく解説されています。
空想世界をつくる理科の教科書の目次

空想世界をつくる理科の教科書の目次

空想世界をつくる理科の教科書の目次
学生の頃に今やっている勉強って将来何の役に立つのだろう、と思ったことがあります。たとえば、数学のサイン・コサイン・タンジェントとか実生活に役立つシーンがあるの? と思っていました。
しかし、大人になると実はあの頃勉強していたことが役立つことがけっこうあります。サイン・コサイン・タンジェントなんかはCSSの関数として実装され、多くの制作者が大人になって使用しています。
話がすこし逸れていまいましたが、本書に登場する数学、物理、地学、生物学など、まさに創作に役立つ知識に溢れています。
献本の御礼
最後に、献本いただいた技術評論社の担当者様に御礼申し上げます。
当サイトでは随時、献本を受け付けています。
お問い合わせは下記よりお願いいたします。
sponsors