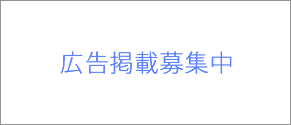Web制作のディレクションに必要な知識とノウハウがまとめられたオススメの本 -Webディレクションの最新常識
Post on:2014年8月22日
sponsorsr
Webディレクターの人だけでなく、デザイナーやコーダーなどの制作者から、プロデューサーやプロジェクトマネージャ-まで、Webプロジェクトに携わる人全てにオススメしたいWeb制作のディレクションに必要な知識とノウハウを網羅的にまとめた『現場のプロが教える Webディレクションの最新常識』を紹介します。
ディレクションとはディレクターの職務ではなく、Web制作者にとっての必須スキルです。

Webのディレクションって他はどうやっているのだろう? もっとうまい方法がないかな、とか気になりますよね。
AmazonではKindle版の現場のプロが教えるWebディレクションの最新常識も扱ってます。お値段はかなりお得!
発売を記念して来週末8/31に、執筆陣によるイベントがあります!
詳しくは下記ページをご覧ください。
まだ30人くらいの空きがあるようです(2014/8/22現在)。
イベントは、本書の内容を更に掘り下げるもので、刺さる企画を生み出すアイデア発想法、制作を円滑に進めるため進行管理、Webサイト・サービスが抱えるコンテンツのお悩み相談など、満載です。
では、そんな本書の中身を紙面のキャプチャで少しだけご紹介。

本書はWeb制作に必要なディレクションのノウハウやワークフローの現状とこれからを網羅的にまとめたもので、すぐ見ることができるように手元においておきたい一冊です。

序章プラス4章の構成で、序章「制作ワークフローの変化」。デザインや技術のトレンドも変わりますが、それに対応してワークフローも見直す必要があります。
本書の特徴の一つとして重要な箇所にマーカーが引いてあるので、ポイントをしっかりと押さえて読み進めることができます。

チーム内でメンバーの作業の切り分けを固定的に考えるのは、失われつつあります。
デザイナーはデザインの仕事のみではなく、ディレクションもできるデザイナー、マークアップも理解しているデザイナーの価値が上がってますよね。メンバーの職名だけでなく、どんなスキルをどんなレベルで持っているかそのキャラクターを把握し、チームを構成する必要があります。

今までディレクターは主に制作フェーズを中心に役割を担っていましたが、これからはプロジェクトの設計から運用フェーズまで、全工程の詳細な要件を理解しているディレクターが求められています。

第1章は「企画提案」。
ディレクションが必要となるのは制作時のみだけでなく、企画時の上流工程でのディレクションも大切です。上流工程のしわ寄せは、制作時に大きな負担となり、チーム内やクライアントの認識のずれや共有不足はトラブルの引き金となります。

作業の助けとなるツール紹介も充実しています。
動くモックアップを作成できる「Prototyper」。静的なデザインだけでなく、操作性や動きを見せることで早い段階でいろいろと検討できるようになります。

また、見積もりも非常に大きなポイントです。Webは形のない商品なので、納得のいく金額を設定するのは難しいと思われがちですが、段階を踏むことで納得感が高い見積もりを提出することができます。

第2章は「設計」。
コンテンツをユーザーにどのように伝えるか、ワイヤーフレームだけではなく、制作・運用を円滑に進めるための設計段階で行うべきことをチェックしましょう。

こういったチェックリストを用意しておくと、便利ですね。

ワイヤーフレームは単に要素を並べるだけのものではありません。情報をグルーピングし、重要度を決め、デスクトップ・スマフォのデバイスに応じたコンテンツ設計を行います。

設計の事例も豊富に掲載されています。キャプチャはレイアウトパターン、実例とともに掲載されているので、レイアウトのイメージを正確に捉えることができます。

アクセス解析ツールのGoogle Analytics、ディレクターとしてどのデータをどのように活用するのか、こういったノウハウも見逃せません。

第3章は「制作・プロジェクト管理」。
プロジェクトを成功させるには、円滑な進行は非常に大切です。ディレクターが現場を理解し、制作環境の変化に対応していけるようにしましょう。また、より効率的に制作を進めるためには、ツールの存在は欠かせません。制作ルールの策定、コミュニケーションや管理、確認・検証などに役立つツールも豊富に紹介されています。

プロジェクトの進行を明確に管理することで、プロジェクトはスムーズにいきます。

クライアントやチーム内のコミュニケーションもディレクターには欠かせないスキルです。課題を与える、フォローやアラートを適切に使うなど、対人スキルのヒントとなるでしょう。またツールを使った進捗管理や情報共有なども使いこなしたいですね。

アサインすることと同じくらい重要なのが、タスクがきちんと完了できているかの確認です。投げっぱなしはよくありません。テスト項目を洗い出し、検証を行い、納品後でも見える形に残しておきます。

最後の第4章は「運用・効果測定」。
Webサイトは、安全に運用されていくというのが非常に大切です。納品後もしっかりとしたケアをすることで、クライアントとの長いおつきあいに繋がります。

最近のWebサイトで欠かせないのはソーシャルサービスでしょう。Facebook, Twitter, Lineなど、闇雲に対応するのではなく、しっかりとした目的をもち、企画を進めます。

Webサイトの効果を計るのに解析ツールは欠かせません。主要な解析ツールの紹介とそれぞれで何ができるのか、簡潔にまとめられています。
現場のプロが教えるWebディレクションの最新常識の目次
-
- 制作ワークフローの変化
- デザイン・技術のトレンドとワークフローの変化
- 職域があいまいになる中での理想のチーム構成
- 新しいWebディレクションに求められるものとは?
-
- 企画提案
- 上流工程のディレクションで見極めるもの
- 企画提案を行う上で持つべき視点とは
- 事前の調査・分析とヒアリングのポイント
- アイデアを「提案できる企画」へ設計していくには?
- 提案するための企画書作成のポイント
- 動くモックアップを作成する「Prototyper」
- 見栄えのよい資料作成に役立つ素材サイトやツール
- 「Webサイトの見積もり」に関するアイデアと例
-
- 設計
- Webサイトの設計段階で満たすべきものとは?
- 設計段階で必ず押さえておくべき6つの要件
- コンセプト設計とその重要性
- プロジェクトの方向性を定める「コンセプト設計」
- ユーザー視点を具体化するカスタマージャーニーマップ
- メタ情報を最適化してページ設計のポイント
- 効果を最大化するページ設計のポイント
- 設計段階におけるビジュアルデザインの捉え方
- jQueryを使った視覚効果と導入のリスク
- Ajaxを導入するメリットと注意点
- 主要なCMSの紹介
- プロジェクトスタート前に確認すべき開発環境
- 外部サービスとの連携
- レンタルサーバーの種類と選定のポイント
- 説得力のある工数と予算を算出するには?
- Google Analyticsの基本機能
-
- 制作・プロジェクト管理
- 制作現場の状況の変化とその背景
- 制作を円滑に進めるための6つのフェーズ
- 工程の切り分けと各段階で行うべきタスク
- 対クライアントに向けたルールの策定
- 制作スタッフ間でのルールの策定
- 担当者にタスクを上手にアサインするには?
- ディレクションする側に求められる知識とスキル
- タスクや成果物を的確に評価・確認するには?
- 納品・公開後に注意すべき点
- Webブラウザ対応をどう考えるか?
-
- 運用・効果測定
- 考慮しておくべきWebサイトのセキュリティ対策
- Facebookページの開設時に留意すべきポイント
- 事前に定めるべき運用ルールともしもの場合の対応方針
- 目的やターゲットによってSNSを選定する
- 制作時のデグレードや対応漏れの防止策
- クライアントとの契約のあり方を見直す
- チームで行うサイト分析と改善提案のポイント
- 解析ツールの数値を生かして効率的にPDCAを回す
- 主要な解析ツールの紹介
- リニューアルすることのリスクを考える
- 現在のSEOの潮流を押さえる
- ディレクション段階でやるべきSEO施策の具体例
-
- 付録
- ディレクション業務に活用できる便利ツール
現役のディレクターでもこうやってディレクションの内容をひとつ一つ言葉にするのは難しいものです。
会社で一冊、チームで一冊、個人で一冊、揃えておきたいですね。
献本の御礼
最後に、献本いただいたMdNコーポレーションの担当者さまに御礼申し上げます。
当サイトでは随時、献本を受け付けています。
お問い合わせは下記よりお願いいたします。
sponsors