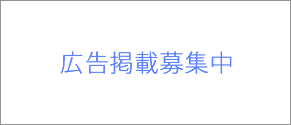こんな良書があったとは!絵が苦手な人でも立体感のある描き方が身につく -鉛筆一本ではじめる光と陰の描き方
Post on:2019年4月12日
sponsorsr
これまで絵を描いたことがない人、簡単な絵は描けるけど立体感のある絵は無理という人にお勧めの本を紹介します。
絵を描くための線の描き方からはじまり、ものの形のとらえ方、モノクロでの色の表現方法、奥行きの表現方法、明暗や質感の描き方まで、絵を描く方法は感覚的な説明になりがちですが、その手順がロジカルに説明されているので非常に分かりやすいです。

本書は当ブログでも何度か紹介した「線一本からはじめる伝わる絵の描き方 ロジカルデッサンの技法(Amazonで見る)」の続編です。前書もかなりの良書でしたが、今回は『光と陰の描き方」とある通り立体的な絵の描き方が詳しく説明されています。
前書を持っている人はもちろん、持っていない人でも楽しめる一冊です。
Kindle版は少しお値段がお得です。
紙面のキャプチャで、中身を少しだけご紹介。

本書で絵を描くのに必要なのは、紙と鉛筆です。コピー用紙でもノートでも、シャープペンシルでも大丈夫です。消しゴムも用意しておくとよいでしょう。

スケッチを始める前に、鉛筆・シャープペンシルの持ち方から、さまざまな線の描き方を学びます。正円をフリーハンドで描くのって、けっこう難しいですよね。でも、描き方の手順が細かく分解して説明されているので、誰でもできるようになると思います。

絵を描くには、ものの形をとらえることが重要です。一見難しそうなものでも、構造や印象を観察し、形の特徴を描くためにどこを注目すればよいのか詳しく解説されています。

鉛筆でも色の違いを表現することができます。紙と鉛筆の白と黒の階調を使い分けることで、明暗や遠近感、そして色さえも表現することができます。

複雑に思える奥行きの表現も本書を読むと、そのロジックがよく分かります。ものの構造を立体的に理解できると、白と黒の階調で作り出した濃淡で奥行きを表現できます。

ものの形や大小の変化で距離感をだすこともできます。透視図法と呼ばれるテクニックです。よく使用されるのは1点透視図法・2点透視図法です。これらのテクニックも手順ごとに詳しく描き方が解説されているので、すぐに試したくなると思います。

本書も半ばを過ぎると、明暗の描き方など自分の描きたいもののスケッチが始まると思います。見たままの形を描いただけでは立体感は伝わりません。

消しゴムは補助線や失敗した線を消すためだけのものではなく、鉛筆と同じように絵を描くための道具としても利用できます。

ものの形のとらえ方、モノクロでの色の表現方法、奥行きの表現方法、消しゴムの使い方などが分かると、描くのが難しい逆光の表現も立体的に描けます。

質感を描けるようになると、絵にリアリティが出せるようになります。本書では異なる素材の質感を描き分けるテクニックも学べます。

堅い金属の質感、柔らかい布の質感、ガラスの透明感の描き方など、手順ごとにそのロジックが詳しく解説されています。

最後の章では光と陰を加えることで、立体感だけでなく、時間の経過も描けるようになります。確かに同じ場所でも朝の光と夜の光は、違いますよね。
鉛筆一本ではじめる光と陰の描き方の目次
- 絵の描き方を知ろう
- ものの形をとらえよう
- モノクロで色を表現しよう
- 奥行きを表現しよう
- 明暗を描こう
- 質感を描こう
- 光と陰を描こう
本書を手に取れば、今まで絵を描いたことがない人でも、挫折せずに描けるようになると思います。絵を描く方法は感覚的な説明になりがちですが、その手順が細かく分解され、ロジカルに説明されているので明確に分かります。
献本の御礼
最後に、献本いただいたインプレスの担当者さまに御礼申し上げます。
当サイトでは随時、献本を受け付けています。
お問い合わせは下記よりお願いいたします。
sponsors