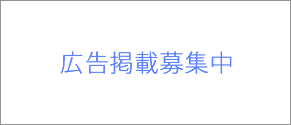どういったデザイン思考で作ったらいいか「伝えるためのデザイン」に着目してデザインのテクニックを学べる良書
Post on:2024年11月8日
sponsorsr
※本ページは、アフィリエイト広告を利用しています。
表紙をぱっと見ると、デザイン書とは違うのかな?と思うかもしれません。プロのデザイナー向けかと聞かれたら違いますが、デザインを学んだことがなくてもデザインするために役立つ知識やテクニックを学べるデザイン書を紹介します。
どういったデザイン思考でデザインをしたらいいのか、特に「伝えるためのデザイン」に着目してデザインについて学べます。

本書は昨日発売されたばかり!
デザイナーじゃない人向けの本ですが、デザイナーじゃない人だけでなく、デザイナーの人にも振り返る意味でお勧めの本です。当たり前のようにしていることでも改めて言葉での説明を読むと、より考えが深まると思います。
Kindle版も発売されています!
版元様より許可をいただいたので、紙面のキャプチャを少しだけご紹介。

本書は5章構成で、デザインの基礎、Webデザインや紙デザイン、文字組みなど、伝えるデザインのために役立つ知識やテクニックを学べます。紙面のデザインはかわいいですが、本書のテーマは「デザイン=かわいい・おしゃれ・スタイリッシュ」ではなく、「伝えるためのデザイン」です。

「伝えるためのデザイン」とは、たとえば素敵なデザインにするだけではビジターは喜びません。そのプロダクトやサービスと世界観が一致しており、伝えるべきことを正しく伝えられるようにデザインすることが大切です。

フォームの入力手順をデザインするときに、ブロックでステップごとに分けたり、アイコンを加えたり、アイコンの代わりにタイトルを加えたり、モノクロでも分かるようにしたり、視線が右に流れるように枠をデザインしたり、伝えたい情報の優先順位でデザインにもいろいろなやり方があります。

第2章は、デザインでよくあるあれって何?
デザインを確認してもらったら「なんか違う」と言われたことはありませんか。この原因は依頼側とデザインのイメージが共有されていないからです。そして依頼側には具体的なイメージがある程度あり、それが言語化されて伝わっていないということです。デザインに入る前に、イメージを言語化して共有し、一致させるという工程が大事です。

「もう少し抜け感が欲しいね」と言われたことはありませんか。抜け感とは、程よく力の抜けたとか、完璧になりすぎないようにわざと少し外すとか、柔らかい・リラックスした印象です。

抜け感はたとえば、右ページ上のバナーは抜け感がほぼゼロのデザインです。濃い色が多めの図形や太い枠線は思い印象を与えます。下のバナーは抜け感が多めのデザイン、枠線は細めやドットにし、ベタ塗りをやめ、空白スペースが増えています。

第3章からはいよいよ具体的なデザインです。まずは、紙のデザイン。名刺、ポスター、パンフレットなど、何のためにデザインして、何を伝えるためにデザインするのかを意識しながら、デザインしていきます。たとえば、名刺だと単にシンプルにかっこよくデザインするだけでなく、文字にメリハリをつけてデザインし、情報を適切にまとめます。電話やメールなどは、アイコンを使ってもいいですね。

第4章は、Webデザイン。Webサイト、スマホアプリ、動画のサムネイル、バナー、SNSの投稿など、目的ごとにデザインのポイントも変わります。

たとえば、スマホアプリのメニュー。左がビフォーで、右がアフターです。左も楽しげなデザインでよさそうですが、右の方がボタンの操作に迷うわないようにデザインされています。

デザインのポイントになるのが、ボタンの大きさと配置、重要なボタンが目に留まるようなデザインになっていることです。これはスマホアプリのメニューなので、右手親指の位置に近い場所(右下)に重要なボタンを配置しています。また、横長から縦長に変更することで、タップがしやすくなっています。他にも、色同士が引き立つ配色方法、信頼感を与えるフォントやアイコンの使い方なども詳しく解説されています。

最後の第5章は、文字組み。紙はもちろん、Webでも文字組みはデザインで非常に重要です。そしてキャッチコピーのテキストも非常に重要です。同じデザインでもどのようなコピーを使用するかで届く相手は変わります。

文字を組むときにもう一つ重要になるのが、フォントです。デザインに使用するフォントで、印象が大きく変わります。たとえば、明朝体を使用すると高級感がでたり、ゴシック体を使用するとカジュアルさがでたり、丸ゴシック体を使用するとかわいらしさを演出できます。本書では、どのような文字組み・コピー・フォントを使用すると伝わるデザインになるのかがさまざまな事例を元に解説されています。
会社のデザイン業務困ったさんに贈る本の目次

会社のデザイン業務困ったさんに贈る本の目次

会社のデザイン業務困ったさんに贈る本の目次
この本を読んで一番驚いたことは、デザイナーじゃなくてもこんなにデザインのことをするんだです。いやもう完全にデザイナーの仕事ばかりで、これだけでできたらデザイナーを名乗っていいのではと思いました。本書を読むと、デザイナーとしての知識やテクニックまでもしっかり学べます。
献本の御礼
最後に、献本いただいたインプレスの担当者さまに御礼申し上げます。
当サイトでは随時、献本を受け付けています。
お問い合わせは下記よりお願いいたします。
sponsors