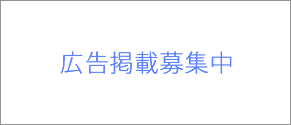色の組み合わせがよく分かる!あの伝説の授業が完全書籍化された配色の知見を広めたい人にオススメの本 -配色の設計
Post on:2016年7月15日
sponsorsr
色の組み合わせや配色は最近では便利なカラーツールもあり、特に知識がなくてもいい感じの色を手に入れることができます。また、センスがある人は色を並べるだけでよい配色になるかもしれません。
しかし、自分なりの配色、望みどおりの配色効果を得るためにはそれでは足りません。
色を見る力を養い、色の組み合わせについてその本質を身につけることができるオススメの本を紹介します。

本書は伝説の授業と言われる「Interaction of Color」の50周年記念版(2013年刊行)の完全日本語翻訳版で、色と色の組み合わせ、色と色のあいだで起きていること、色のインタラクションについて学べる一冊です。
そんな本書の中身を少しだけ紹介します。

本書は色の本質を学び、といってもカラーシステムや色のルールを機械的に学ぶのではなく、色を見ることを理解し、色の形と配置による色と色との相互作用の視覚表現から、色の相互依存の認識について、テキストと演習で学べます。
上の目次は、色を見ることについてのテキストの部分です。

色を効果的に使うためには色を知ることが大切。色を識別できないと、色を扱うことはできません。カラーホイール・色相環などはひとまずおいて、まずは色を見る力を養います。デザインやイラストで普段、無意識におこなっていることでも言語化されたものを読むと、より理解が深まり、新しい発見に出会えます。

色はひとつだけを使うということはまずありません。白黒でも白と黒を使います。そして色を組み合わせることで、さまざまな相互作用を生み出します。

そして、色の組み合わせは質や量や配置によって効果が大きく変化します。
色の組み合わせ方や配色がもたらすインタラクションを、実際の例を見ながら演習で学んでみましょう。
以下の演習と図版は版元様から画像を提供いただきました。

色は組み合わせる色によって、その色が異なるように見えます。同じ色なのに違うように見える画像をネットで見たことがあると思います。これは色の相対性と呼ばれるものです。配色する際には、それぞれの色の本質だけで選択するのではなく、その組み合わせ方が重要です。

明度に変化をあたえたグラデーションでは多くの人がその明るい・暗いを間違わずに認識することができます。しかし、彩度は色の好みもあり、多くの人が同意見になることはありません。青と赤で、それぞれの色相を代表する色はどれですか?

色にはその表面の色を認識するだけでなく、フィルム・カラーとボリューム・カラーの2つの自然現象があります。
フィルム・カラーとは目と対象物の間にある半透明なレイヤーとして見える色で、例えば太陽が日中は白く輝いて見え、夕方には赤く見える現象です。ボリューム・カラーは液体に知覚される色彩で、水面の上は白く見え、深くなるほど碧く見える現象です。これらは人間の生理や心理に影響を受けたものではなく、物理的な現象です。

色を塗り重ねる時に、面白い現象が見られます。2, 3回色を重ねた時には2, 3回分の効果が見られますが、重ねる度に効果が薄れるため、5回重ねた効果をだすためにはそれ以上の回数が必要になります。

明度が同じで、コントラストが類似した色を組み合わせる時にも、非常に面白い現象が見られます。特定の配色をすることで、色と色のはっきりした境目がほどんど見えないようになります。
配色の設計の目次
- 色の記憶- ヴィジュアルメモリー
- 色の読解と構築
- なぜカラーペーパーか- 絵の具の代わりに
- 色はたくさんの顔を持つ- 色の相対性
- 明るいか暗いか- 光の強さ(明度)
グラデーションの研究- 新しい表現方法
色の強さ(彩度) - 2色としての1色- 地色を入れ替えることで見える色
- ふたつの色を同じように見せる- 色の引き算
- なぜ色はだます?- 残像と同時対比
- 紙による混色- 透明性の錯覚
- 現実の混色- 加法混色と減法混色
- 透明性と空間錯視|色の境界と可塑作用
- 光学的混色- 同時対比の再考
- ベツォルト現象
- 色の間隔と移調
- 中間混色ふたたび- 交差する色
- 色の並置- 調和──量
- フィルム・カラーとボリューム・カラー- ふたつの自然現象
- 自由研究- 想像への挑戦
ストライプ- 制限された並置
紅葉の研究- アメリカでの発見 - 巨匠たち- 色の楽器
- ウェーバーとフェヒナーの法則- 混色の測定
- 色の温度
- 揺れる境界- 強い輪郭
- 等しい光の強さ- 境界の消失
- 色彩理論- カラーシステム
- 色彩を教えるにあたって- 色彩の用語について
- 参考文献に代えて- 私の最初の協力者
色、色の組み合わせ、配色について知見を広めたい、深く学びたい、すべてのデザイナー・イラストレーター・アーティスト、そして絵師さんたちにオススメします。
献本の御礼
最後に、献本いただいたビー・エヌ・エヌ新社の担当者さまに御礼申し上げます。
当サイトでは随時、献本を受け付けています。
お問い合わせは下記よりお願いいたします。
sponsors